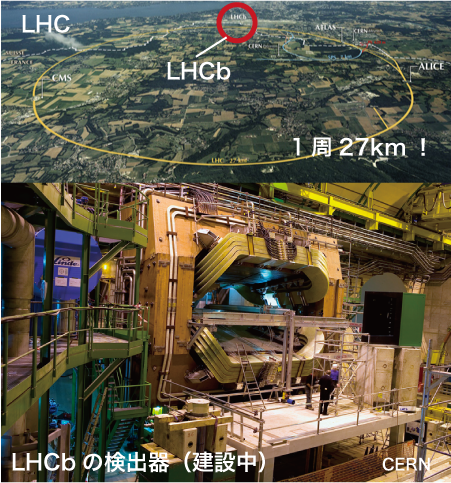第1章 文体とは「配置」である
文章(文体・style)は思想を彫らねばなりませぬ。それゆえ名文を書くためには主題に精通せねばなりませぬ。これにじゅうぶんの省察を加え、もって思想の秩序をはっきりと見極め、思想に適当の順序をほどこし、おのおのが一個の観念を表示するところの連鎖を作らねばなりませぬ。(「ビュフォンの文章講演」)
文章の書き手がある主題について考えたこと(思想)とその配置こそ文体の本質であり、これは他人が盗み取れるものではない。というのも、文体とは人がものを考える際に設ける秩序と運動なのだから。
文章を書く人がどんな言葉を配置するかという点については、おのずとその人の経験と記憶が問題となる。人が文章を書く際に用いることができるのは、基本的に自分の脳裡に収まっている言葉だけである。私たちは文章を書くつど、それまで目にしてきた言葉や耳にしてきた言葉の経験とその記憶を活用して、そこから組み合わせを生み出している。言い方を変えれば、自分の記憶こそが言葉を選び出す際の母体である。
第2章 文体の条件―時間と空間に縛られて
第3章 文体の条件―記憶という内なる限界
そもそも言葉というもの自体が、さまざまな事物や経験を、コンパクトに圧縮保存するための記憶装置のようなものだ。言葉が記憶を圧縮して保存しているようだ。言葉がきっかけとなって、人間の脳裡に収められた記憶が顕在化するといったほうがよい。言葉とは、記憶に蔵された何かを引き出すための鍵のようなものだ。第4章 対話―反対があるからこそ探求は進む
ガリレオ・ガリレイの「天文対話」。正式な書名はもうちょっと長くて「プトレマイオスとコペルニクスとの二大世界体系についての対話」という。
何かを「知る」とはどういうことか、これが対話の隠れた主題なのだ。
▼
なぜわざわざ対話にするのだろうか。ガリレオは、対話形式を採る利点をこう述べている。
「対話であれば数学上の法則に入念な注意を払わねばならぬということはなく、またときとすると主要な論証に劣らず興味のある脱線の余地も多いからです」
同じことを論文のような独話体で書こうと思ったら、数学的論証を細かいところまできっちり書いてしまわねばならない。この書物で検討したいのはそうしたことではなく、むしろ「天地のいずれが動いているのか」という大問題をどういう理路で考えるかという道筋だ。
対話なら「主要な論証に劣らず興味のある脱線」ができる。そもそも脱線とは何だろうか。一体どういう立場に立つと、ある議論が「脱線」していると感じられたり、そう判断できるのだろうか。それは、進むべき「本線」がすでに決まっている場合だ。
ことにある問題を巡って、決定的な結論が予め分かっていないような場合、つまり、到着点が見えないまま、探りながら進んでいくような場合、そもそもなにが「脱線」でなにが「本線」かということは、事の次第からして決めることはできない。そのような見方ができるとすれば、どこかに到着した後で、辿ってきた足跡を振り返ってみて、「ああ、ここに来たいのなら、もっと近道があったな」と事後的に「本線」と「脱線」を発見することだろう。だが果たして、その「脱線」がなければ、今立っている場所に辿り着いたかどうか、定かではない。
一つの問題を巡って、三人の人物がときに意見を対立させて歩み寄ったり行きつ戻りつしながら、共に試行錯誤してゆくその様こそが、ぜひとも必要だったのである。
対話という形式であれば、私たちの日常的なおしゃべりがそうであるように、話はあちらこちらへ遊んでよい。むしろ、対話の醍醐味は、独話では隠されてしまいがちな右往左往の過程、ああでもないこうでもないという試行錯誤の過程そのものを俎上に載せやすいという点にある。一足飛びに「結論」だけを欲しがるのではなく、どんな検討や試行錯誤を経て、その結論へと至ったのかという道筋を示せるのだ。ガリレオが、対話なら脱線できる余地があると言ったのは、恐らくこうした意味なのだろう。
▼
この対話の場では、参加者相互の間に何が生じているのだろうか。「天文対話」を見る限り、サルヴィアチとシムプリチオは、互いに同じ意見に達して合意したりはしていない。しかし、「天文対話」が素晴らしいのは、むしろ議論が決着しないところにある。容易には分かり合えない者同士が向き合っているからこそ、自分にとっては自明と思えることも、意見の違う相手に向けてきちんと言葉にしたり、対話の過程を通じて、様々な角度から検討が重ねられてゆくのである。
▼
二人の人がいて、互いに考えることが部分的にであれ「一致する」とはどういうことなのだろう。異なる人間は、当然のことながら異なる人生を歩み、異なる来歴を持っている。脳裡にある知識や経験やものの考え方、記憶のあり方は、人それぞれで違っている。そう考えると、むしろ人々が合意できること、理解し合えることのほうが不思議にさえ思えてくる。
自分の言葉がどのように受け止められたかを、直接確認する術はない。他人の頭の中を覗くことはできないし、心中なにが渦巻いているかを知ることはできない。ただ、サグレドやシムプリチオの言葉や表情や身振りといった外面に現れて、こちらにも知覚できるなにかを見聞きして、推し量る他はない。虫の居所や何を信じたいと望んでいるかといったこと、感情や信念が事態をいっそう複雑にする。
他人が何を考えているのかは分からない。というよりも、何がどうなったら他人の考えが分かったことになるのかということさえ、実はよく分からない。
私たちは言葉を使うとき、自分が言わんとすることを、既成品である言葉という鋳型に流し込み、組み合わせて提示しているのである。人の脳裡心中は分からないという大問題については、後で「小説」について考える際に、もう一度真正面から向き合うことになる。
それでも対話を続けているのが面白い。理解より無理解があるからこそ、互いの違いがいっそうはっきりと浮かび上がり、問題点が鋭く顕わになる。意見が一致せず、すれ違い続ける。だからこそ、対話は続く。言葉を尽くすほど、互いに脳裡で考えていることがより多角的に現れてくる。
▼
現在、書物のほとんどは独り言のように書かれている。それを書いたり読んだりするのはどういうことなのか。その独り言を入れて移動できるように形を与える書物とは何なのか。実は、本書全体の底には、このようなぼんやりとした疑問がある。
第10章 小説―意識に映じる森羅万象
その世界に存在しているということは、猫が思い出せる前にどこかで生まれたのであり、最初の記憶がある時点までの間も、なんらかの生活を営んでいたはずである。しかし、記憶を語る以上、思い出せないことは語りようもない。つまり、猫の記憶、しかもそうしようと努めて思い出せる記憶が、この語りの材料のすべてである。猫が経験しても記憶していないこと、記憶には刻まれていても思い出せないことは、語りたくても語れないのである。そうした記憶が蘇るには、きっかけが必要だ。例えば、ある男が紅茶に浸したマドレーヌの風味から、長い長い記憶を想起するように。
主に二つのことに注目した。一つは、書かれていることと書かれていないこと。もう一つは、この場面の時間の流れ。いずれも、小説という種類の文章について考える上で、非常に重要な点である。
書生が猫を見つけて拾い上げるまでのあいだ、一匹と一人、そして両者が存在する場所を構成するあらゆる物事とその変化、時間とともにそこで生じるすべての出来事のうち、カメラで撮影できるものだけが映像に映る。内心のようにカメラで撮影できないものは映らない。仮に、この映像に映る様子が全体だとしたら、先ほどの文章に表されているのは、その一部だ。書かれていることに対して、書かれていないことが膨大にある。
作家は小説を書くにあたって、必ず取捨選択を行っている。ある情景を書くとき、すべてを書き尽くすことはできないとしたら、何を書くのか。どのような言葉で書くのか。言葉をいかに配置するのか。ここにこそあらゆる小説の秘密がある。小説の文には、書き手がどのように世界を見ているか、どんな経験を重ねてきたか、どのような言葉を脳裡に蔵しているか、そういったことが否応なく現れるのである。それがいわば作家の「文体(style)」を形作っている。だから、仮に「同じ」場面を描くとしても、書き手が何に注目して、何を取り、何を捨てるか、それをいかなる言葉で表すか、つまり選択と省略の仕方によって、まるで異なる状況が描き出されることになる。
小説の文章は、複数の視点や時空間が撚り合わされている。そうした複雑な状況が、厳しく取捨選択された言葉で編まれている。
本を手に取り、小説を読み始めると、一本の線状に並んだ言葉に沿って、目と意識が働き、手はその流れを助けるようにページを繰る。小説に没頭すればするほど、最前まで次々と私の注意を奪い去っていったざわめきが背後に退いてゆき、言葉の流れにすっかり心身を委ねることになる。その言葉の綾をたどる読者の心中で、ある出来事が生じ、変化してゆく様が浮かんでは消え、ある気分が催される。小説とはそのような一種の秩序を与える言葉の装置なのだ。その秘密の鍵は、人間の「意識」の中にある。
主に二つのことに注目した。一つは、書かれていることと書かれていないこと。もう一つは、この場面の時間の流れ。いずれも、小説という種類の文章について考える上で、非常に重要な点である。
書生が猫を見つけて拾い上げるまでのあいだ、一匹と一人、そして両者が存在する場所を構成するあらゆる物事とその変化、時間とともにそこで生じるすべての出来事のうち、カメラで撮影できるものだけが映像に映る。内心のようにカメラで撮影できないものは映らない。仮に、この映像に映る様子が全体だとしたら、先ほどの文章に表されているのは、その一部だ。書かれていることに対して、書かれていないことが膨大にある。
作家は小説を書くにあたって、必ず取捨選択を行っている。ある情景を書くとき、すべてを書き尽くすことはできないとしたら、何を書くのか。どのような言葉で書くのか。言葉をいかに配置するのか。ここにこそあらゆる小説の秘密がある。小説の文には、書き手がどのように世界を見ているか、どんな経験を重ねてきたか、どのような言葉を脳裡に蔵しているか、そういったことが否応なく現れるのである。それがいわば作家の「文体(style)」を形作っている。だから、仮に「同じ」場面を描くとしても、書き手が何に注目して、何を取り、何を捨てるか、それをいかなる言葉で表すか、つまり選択と省略の仕方によって、まるで異なる状況が描き出されることになる。
小説の文章は、複数の視点や時空間が撚り合わされている。そうした複雑な状況が、厳しく取捨選択された言葉で編まれている。
本を手に取り、小説を読み始めると、一本の線状に並んだ言葉に沿って、目と意識が働き、手はその流れを助けるようにページを繰る。小説に没頭すればするほど、最前まで次々と私の注意を奪い去っていったざわめきが背後に退いてゆき、言葉の流れにすっかり心身を委ねることになる。その言葉の綾をたどる読者の心中で、ある出来事が生じ、変化してゆく様が浮かんでは消え、ある気分が催される。小説とはそのような一種の秩序を与える言葉の装置なのだ。その秘密の鍵は、人間の「意識」の中にある。
▼
小説には何がどのように書かれているのか。このことを徹底的に考え抜いた人の一人が、夏目漱石だった。彼がロンドン留学を経て、帝国大学で講じた一連の講義、特に「文学論」として後にまとめられた考察は、今もなおこのことを考える上で非常に重要な考え方を示している。
漱石の狙いは、多様なかたちをとる文学全般を、できる限り普遍的に、根底から捉えてみることだった。それを煎じ詰めたのが、同書の開口一番に説かれる「F + f」という定式であり、「文学論」全体がこのことの意味を説くために書かれている。
【 F + f 】(認識)+(情緒)
F:焦点的印象または観念、認識的要素、知的要素
感覚、人事、超自然、知識の4種類に分類できる。
人が何かを思い浮かべること、認識すること。
f:情緒
喜怒哀楽や恐怖、怒り、同情、恋心など。
「F」と言われているのは、「焦点的印象または観念」を記号で表したもの。恐らく「Focal impression or idea」のこと。また、Fを「認識的要素」や「知的要素」とも呼んでいる。もう少し具体的には、感覚、人事、超自然、知識の四種類に分類している。言ってしまえば、人が何かを思い浮かべること、認識することを指している。他方で「f」とは「情緒」であり、こちらは「feeling」を指すと思われる。喜怒哀楽や恐怖、怒り、同情、恋心などがこれに当たる。漱石は、およそ文学作品は人間が思い浮かべる「認識」と、それに伴う「情緒」という二大要素から構成されているというのだ。
満開の桜を眺めて(知覚)
「実にいいものだ」と感じ入る(情緒)
書生という人間の噂を聞き(知覚・知識)
恐ろしいと感じる(情緒)
こうしたさまざまな「F + f」によって、文学は作られているというのである。
▼
「焦点」とは何か。漱石は、当時の心理学(現在でいう認知科学や神経科学とも重なる)を念頭に置いている。
心理学者ウィリアム・ジェイムズの「意識の流れ(Stream of Consciousness)」という捉え方を踏まえている。ジェイムズは、人間の意識とは絶えず流れてゆく川のようなものだと喩えた。
イギリスの心理学者ロイド・モーガンは、その「意識の流れ」という見方に立って、もう一歩を進めた。つまり、人間の意識をさらに積極的に「波」に喩えて表現した。私たちの意識は、時々刻々絶えず波打って流れている。ある事柄が意識に現れたかと思えば、次第に消えてゆき、また別のものが次第に現れてくる。その波の頂点を、モーガンは「焦点(Focus)」と呼んだ。
「焦点」とは何か。漱石は、当時の心理学(現在でいう認知科学や神経科学とも重なる)を念頭に置いている。
心理学者ウィリアム・ジェイムズの「意識の流れ(Stream of Consciousness)」という捉え方を踏まえている。ジェイムズは、人間の意識とは絶えず流れてゆく川のようなものだと喩えた。
イギリスの心理学者ロイド・モーガンは、その「意識の流れ」という見方に立って、もう一歩を進めた。つまり、人間の意識をさらに積極的に「波」に喩えて表現した。私たちの意識は、時々刻々絶えず波打って流れている。ある事柄が意識に現れたかと思えば、次第に消えてゆき、また別のものが次第に現れてくる。その波の頂点を、モーガンは「焦点(Focus)」と呼んだ。
私たちは自分の意識の状態ひとつでさえ、まともに記述することはできない。複雑すぎるし、ジェイムズが喩えたように川のごとく絶えず流れており、移ろう。それに対して、言葉というものは、あまりに粗雑すぎるかもしれない。だが、言葉という既成の鋳型を使うことで、私たちは、そうした変化し続ける波の連続から、なんとかその幾ばくかをすくい取り、固定して、他の人に伝えられるのだ。そして、文学作品では、人の意識の波の一部、意識に浮かぶもの、その波の「焦点」を、言葉で縫い取っている。これが漱石の言う「F」である。
▼
文学においては、何を描こうとも、そこには必ず人間の知覚や思考、記憶、情緒が反映されている。作家は、小説を書くにあたって、自らの意識の流れの中から、ある焦点を選び、それを表す言葉を記憶や辞書に探って選び、言葉の配置を選んで文を成し、文の配置を選んで文章を構成する。描かれる事柄は、人間であれ自然であれ人工物であれ無機物であれ、人間の意識に映じたかたちで表現されることになる。そこには当然のことながら、作家が生きる時代における人間理解、心と体の両面に関して諸学術が明らかにし得たことや世界観が反映されている。
人間の意識の性質を踏まえることこそが、文学なるものの本質に迫ることである。漱石はそう考えた。
▼
文学においては、何を描こうとも、そこには必ず人間の知覚や思考、記憶、情緒が反映されている。作家は、小説を書くにあたって、自らの意識の流れの中から、ある焦点を選び、それを表す言葉を記憶や辞書に探って選び、言葉の配置を選んで文を成し、文の配置を選んで文章を構成する。描かれる事柄は、人間であれ自然であれ人工物であれ無機物であれ、人間の意識に映じたかたちで表現されることになる。そこには当然のことながら、作家が生きる時代における人間理解、心と体の両面に関して諸学術が明らかにし得たことや世界観が反映されている。
人間の意識の性質を踏まえることこそが、文学なるものの本質に迫ることである。漱石はそう考えた。